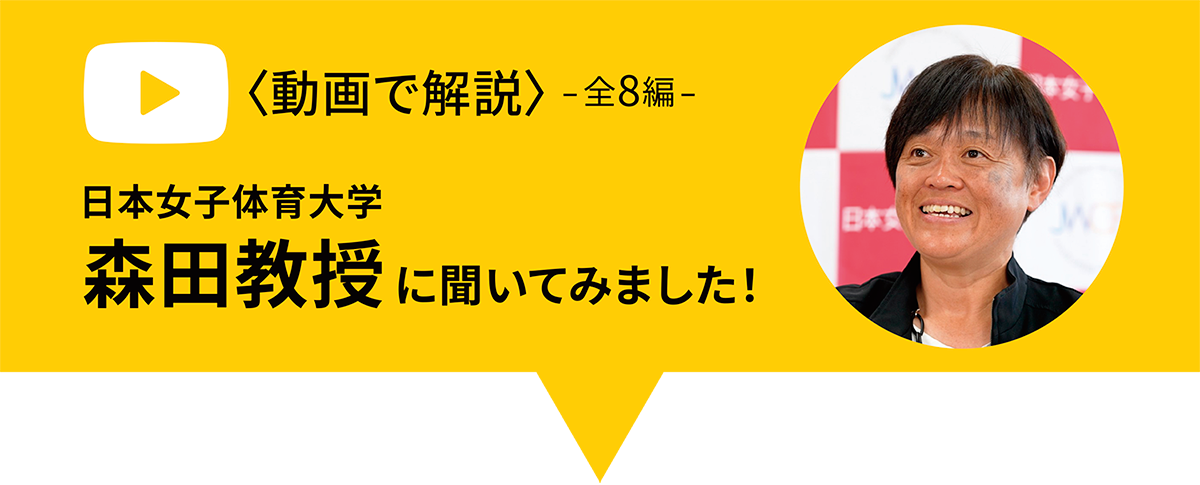『幼児期の運動に大切な要素とランニングバイクの果たす役割』とは
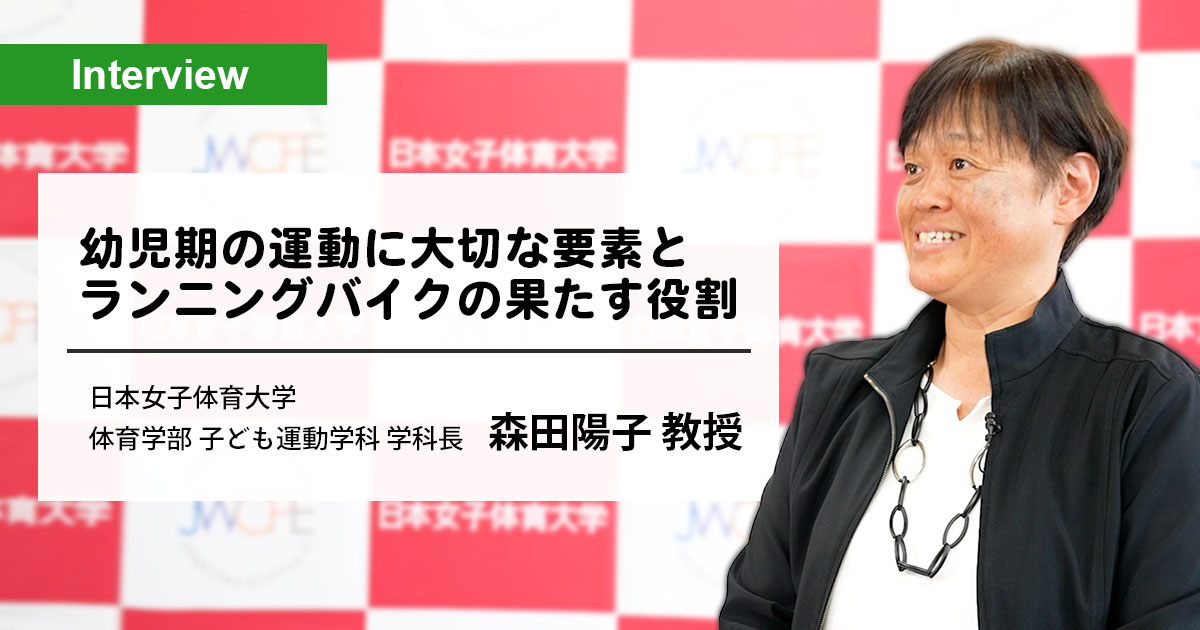
「幼児体育」「運動遊び」の専門家である、日本女子体育大学の森田陽子教授へインタビューを実施し、幼児期の運動に大切な要素とランニングバイクの果たす役割についてお話をお伺いしました。
<プロフィール>
日本女子体育大学
体育学部 子ども運動学科 学科長
森田 陽子(もりた ようこ) 教授
日本幼児体育学会理事
監修:NHK Eテレ「いないいないばぁ!」の体操「ピカピカブ~!」
著書:「0歳児から5歳児 運動遊び12か月」
幼児の生活のすべては「遊び」からはじまる。楽しくなければ興味を示さない
森田教授は「幼児体育」「運動あそび」の専門家で、これらについて研究しています。
森田教授:私が子どもに運動を指導するようになったのは今から30年前のこと。当時、勤務していた大学に附属幼稚園があり、大学の教員が体育の指導を担当することになっていました。中学校と高校の体育の教員免許は持っていましたが、子どもの運動に対する知識はほとんどありませんでした。
指導を始めて10年が過ぎた頃、「自分の指導方法はこれでいいのか?」と疑問を持つようになったと森田教授は振り返ります。楽しそうに取り組んでくれない子どもが目立つようになったのです。これは子どもに問題があるのではなく、自分の指導に問題があるのかもしれないと思い始めた森田教授は、2003年に「子ども」や「保育」を専門とする大学院の門をたたきます。
森田教授:学んでいく中で、子どもの生活のすべては遊びからはじまり、遊びから多くのことを学ぶ、楽しくなければ興味を示さないということに気づかされました。私の指導は、運動をいかに上手に、見栄えよくできるかという部分に主眼を置いていたのかもしれません。子どもたちにとっては、楽しくない苦痛な時間が展開されていたとわかったのです。
こうして、森田教授は子どもが主体的にいかに楽しく、子どもたちと一緒に自分自身も体を動かして遊ぶにはどうすればいいかということに目を向けるようになり、幼児の運動遊びに関する研究を始めました。
外遊びが子どもの健全な成長に欠かせない6つの理由
子どもの健全な成長には外遊びが重要な役割を果たします。
なぜ外遊びが幼児期に必要なのか、森田教授はその理由として次の6点を挙げます。
① 基礎体力が養われる
運動の基礎機能は「走る」「飛ぶ」「投げる」「回転する」「泳ぐ」の5つ。これらの多くは外遊びによって獲得でき、遊ぶことで自然に基礎体力が養われることになります。
② 積極性が育つ
屋内での遊びは限られた場所で与えられたものを使うことになり、小さな遊びにとどまりがちです。屋外であれば、走ったり、跳んだり、投げたりする場所を十分に確保できます。子どもが自分でいろいろな遊びを探し、自分が「これをしたい」と思って遊ぶ、積極性が育ちます。
③ コミュニケーション能力が発達する
公園などに出かけることで、いつもと違う人と出会うきっかけになります。「仲間に入れて!」とほかの人に声をかけたり、逆にほかの人から「一緒に遊ぼう!」といわれて「いいよ!」と返事をすることを繰り返すことで、子どものコミュニケーション能力を育みます。
④ 健康維持に役立つ
太陽の光を浴びることはストレスの発散になり、太陽の光の下で身体を使って遊ぶことで心地よい疲れを子どもは感じます。外遊びによって、ぐっすり眠る、質の良い睡眠を得られます。また、たくさん身体を使って遊ぶことで、お腹がすき、食事もしっかり取れるようになります。
⑤ 失敗経験から学ぶ
外遊びには転んだり、何かにぶつかったりすることが付き物です。子どもは、転ばないようにするには、ぶつからないようにするにはどうしたらいいか考えようとします。失敗経験からの学びによって、 危険を避けるための動きが自然に身についていきます。
⑥ 学習能力も向上する
これは勉強ができるようになることではなく、先を考えて、今、自分がすべきことは何かを考える習慣が身につくということです。さらに、いつもと違う環境の中に身を置くことで、五感をフルに働かせ、脳の前頭前野が刺激を受けるため、集中力のアップも期待できます。
子どもが外遊びを好きになるために、保護者はどのようなことに気をつければいいのでしょうか。
森田教授:特別なことをする必要なく、まずは自由に走り回れるスペースのある広い場所に子どもを連れていくだけで十分だです。
「休日には子どもを外に連れ出してください」とお願いすると、「クルマで遊園地に行かなきゃ」と考えてしまう保護者は少なくありません。でも、何もないところでいいんです。特に小さい子どもは広い場所に連れて行くと、最初「うわー!」っていいながら走り回ります。そして、自分の目で周囲を確認しながら、「ここでこうしたいな」「そうするためには、どうしたらいいのだろう」と、自分で考えながら遊びを展開していきます。
遊園地などでは、自分が何をしたいのかを考えなくても与えられている状況に満足してしまいます。「ここには何もないから、こんなことができるんじゃないか」と考え、想像を膨らませる、このプロセスこそが子どもにとって大切なのです。
人が一生かけて獲得する運動機能の約90%は5歳頃までに身につく
人が一生をかけて獲得する運動機能の約90%は5歳頃までに身につけている
森田教授:幼児期は運動機能の成長が著しく、人が一生かけて獲得する運動機能の約90%は5歳頃までに身につけているといわれています。中でも0歳児の1年間は人の一生で最もたくさんの運動機能を獲得する時期。何もできなかった乳児が寝返りをうったり、ハイハイをしたり、つかまり立ちをしたり、最終的には二本足で立てるようになります。森田教授は1歳になったくらいから、さまざまな場所をたくさん歩くことを推奨します。
運動嫌いが起きる理由と対処法
森田教授:3歳から4歳にかけ、いろいろな経験や失敗を通じて、たくさんの動きを体得していくと、5歳になる頃には、大人とほぼ同じことができます。と同時に(忘れてはならないことは)、5歳頃には「運動嫌い」が出現する年齢でもあります。これは自分と他者を比べられるようになるから。この時期に「あの子と比べて自分は下手だとか、できない」と考えてしまうと、子どもは運動が嫌いになって新しいことに挑戦しなくなってしまいます。大人(保護者)は注意する必要があります。
ここは大人(保護者)の出番です。今できていることを認めて、褒めてあげてください。「今はできないけれども これは上手にできているよ」と声をかけられることで、「やってみたい、やってみよう」と子どものモチベーションが高まります。
幼児の身体機能や基礎体力の向上に役立つランニングバイク
ランニングバイクはスピードを獲得することができる
森田教授:人が身体を動かすには10種類の体力(筋力、瞬発力、持久力、協応性、平衡性、敏捷性、巧緻性、柔軟性、リズム、スピード)が必要です。その中にある「スピード」(身体を動かす速さ)を幼児が獲得するのにランニングバイクは適しています。
ランニングバイクに乗ると、ほかの遊びでは得られないスピードを獲得することができます。また、風を切って走る心地良さを経験できるのはランニングバイクならでは。
幼児期の外遊びの中にランニングバイクを取り入れることは、子どもの身体機能や基礎体力の向上につながります。
「走る」基礎機能を向上させるツール
森田教授:ランニングバイクにはペダルがないため、自分の足で地面を蹴らないと前に進みません。ランニングバイクで遊ぶことは、必然的につま先で蹴るという行為を繰り返すことになります。この足の指を使う運動は脚力を鍛え、「走る」という基礎機能を向上させる効果があります。
走ることは運動の主役。ランニングバイクは、速く上手に走れるようになるためのツールとしても期待できます。そして、ランニングバイクは自分でバランスを取らないといけないので、バランス感覚も遊びの中で自然に身につきます。さらに、体幹が鍛えられ、姿勢も良くなります。また、外遊びにおいて、子どもは転ぶことによって多くの学びを得ます。その点でもランニングバイクは最適です。ランニングバイクで転ぶ場合は、走っていて急に転んだ場合と比較すると、泣き出してしまう子どもが少ないように感じます。重心が立っている時より低いため、転んでもダメージが少ないからです。ランニングバイクのような二輪車は転ぶ感覚をつかみやすいと思います。なぜ自分が転んだのかを感覚的に理解し、どうしたら失敗しないか考えて行動につなげることができるでしょう。
三輪車との違い=楽しく、運動機能が向上する
森田教授:幼児期の乗り物としては三輪車がありますが、三輪車は自分でバランスを取る必要はなく、スピードも出ません。それに比べると、ランニングバイクはスピードを出せるため、子どもは楽しさを感じることができると思います。
ランニングバイクを経験していると補助輪なしの自転車への移行がスムーズ
上半身と下半身で違う動きをすること
森田教授:子どもは2歳後半から3歳くらいで、上半身と下半身で違う動きができるようになります。1歳頃からランニングバイクで遊んでいると、こうした運動機能を早期に体得することが可能になります。
手でハンドルを操作しながら足は地面を蹴るというランニングバイクならではの動作は、まさに上半身と下半身で違う動きをすること。これは将来、スポーツをする時に役立ちます。ボールをつきながら走るなど、スポーツでは上半身と下半身で違う動きをする場面はたくさんありますよね。だから、ランニングバイクは1~3歳の幼児に最適なのです。
ランニングバイクは自転車に近い身体の使い方
森田教授:ランニングバイクは自転車に近い身体の使い方をすることから、そのまま補助輪なしの自転車に移行できる優れた乗り物です。
ランニングバイクを経験していれば、あえて補助輪付きの自転車に乗せる必要はありません。ランニングバイクで既に補助輪なしの状態を体得していますから、自転車への移行はスムーズに行えると思います。
ランニングバイクで遊ぶことで運動有能感を獲得できる
幼児と接する機会の多い森田教授は近年、体幹が備わっていないため、バランス感覚の悪い子どもが増えていることを危惧しています。
森田教授:幼稚園・保育園の中で、同じ姿勢を保持できない子どもを目にします。ランニングバイクによって体得したバランス感覚、体幹は、それを改善できる1つと考えています。
日本女子体育大学には附属幼稚園があり、2022年にランニングバイクを運動遊びの道具の1つとして導入しました。晴れていれば、子どもたちは「外でランニングバイクに乗りたい」と、運動遊びの1つとして定着しているそうです。
森田教授:よく保護者の方から「うちの子が上手く乗れないようなんですけど、どうしたらいいですか?」と質問を受けます。その時、私は「サドルに座っているだけで乗れているじゃないですか。まずは、それを褒めるところから始めましょう」と答えます。足を蹴って前進できたら、これも褒めてあげてほしい。「進んでいるじゃない、すごいすごい!」と。すると、子どもは「えっ、できてる!」と感じ、乗れた気分になってさらに前に進んでいきます。「じゃあ、またやりたい」と続けているうちに、「もっと速く強く前に足を蹴れば、速く進むんじゃないか」と子どもは自分で考えて、さらに上手に乗れるようになっていくのです。
森田教授は身体機能や運動能力の向上だけでなく、運動有能感を育む面でも、ランニングバイクで遊ぶことは有効だと考えています。運動有能感とは、子どもが運動遊びなどを体験した時に感じる「できた」「もっと上手になりたい」「またやりたい」という感情のこと。
森田教授:何度も何度も失敗を繰り返しても諦めずにやればできる、さらに努力すればもっと上手になるという成功体験を幼児期に獲得できれば、将来、スポーツに取り組む時はもちろんですが、この先の人生のあらゆる場面で彼ら彼女らの背中を押してくれる自信となるでしょう。
幼稚園で運動遊びをする時、森田教授は道具の出し入れをとても大切にしています。
森田教授:自分が使うものは自分で準備して、自分が使った後は必ず片付けることを徹底しています。これは次に使う人がすぐに使える状況をつくるためですが、「自分さえ良ければ」ではなく、周囲にいる人のために「自分は何をすればいいか」ということを考えるきっかけになるからです。ランニングバイクは子どもが持ち運びできる重さなので、子ども自ら片づけをすることができます。一人で運べなければ、誰かに助けを求めてもいい。自分一人でできなければ、ほかの人に頼んで協力してもらえばいいという考え方を、遊びの中で身につけることができます。
ランニングバイクで遊ぶ時は、必ずヘルメットを着用するというルールがあります。転んだ時に頭部を保護するためです。
森田教授:以前、私が幼稚園で子どもに混じってランニングバイクに乗ろうとした時、「先生、ヘルメットをかぶらないとダメだよ」といわれたことがありました。子どもたちは安全面への配慮についても、学んでいることに驚かされました。今は、大人も自転車に乗る時はヘルメットをかぶることが努力義務となっています。ランニングバイクで遊ぶ時のルールの1つとして、これを幼児期から習慣にしておくと将来、自転車に移行した際も自分からヘルメットをかぶるようになるでしょう。
このように、ライニングバイクによる遊びを通じて、子どもに社会性を身に付けてもらうこともできるようです。
森田教授:「ドキドキワクワクする」ことは人が生きていく中で大切なことだといいます。「初めてのことにはもちろんドキドキしますね。でも、楽しそうと思えるものであれば ワクワクします。子どもたちにとってランニングバイクには、ドキドキとワクワクの両方があるはずです」。